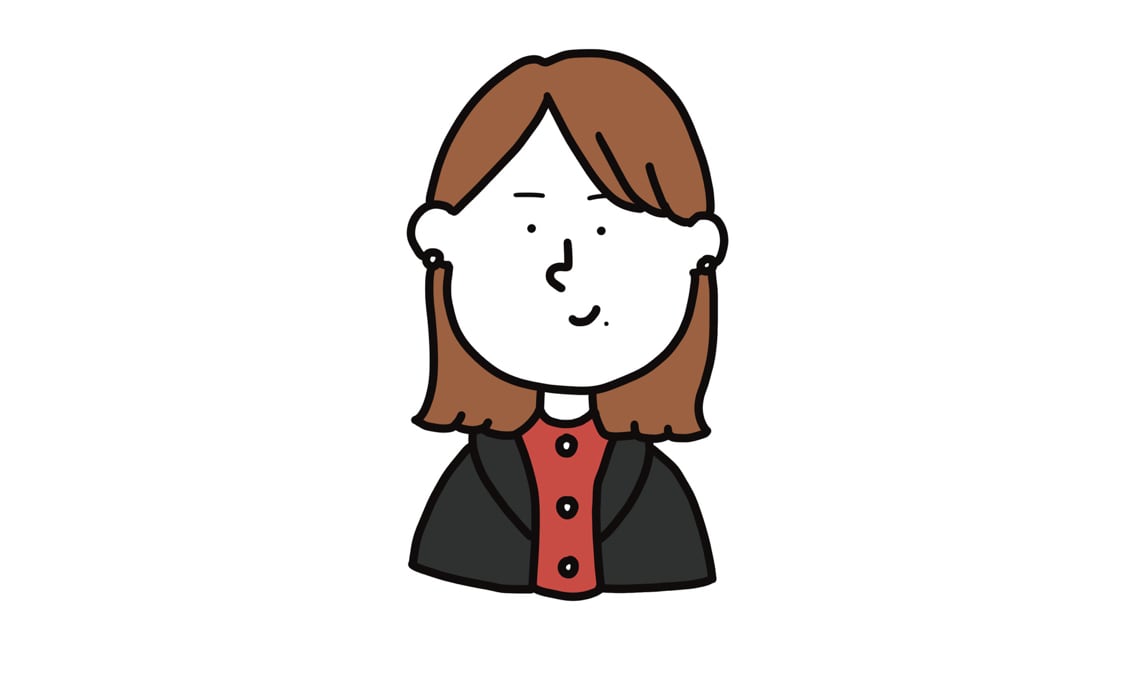張り子職人・吉岡武徳さんがかつて工房として利用していた、神戸・再度山に位置するHARICOギャラリー(旧須磨張り子館)。
そこには、吉岡さんが長年コツコツ作り続けたたくさんの神戸須磨張り子が眠っていました。眠ったままだと勿体無いし、多くの人にこの可愛さを知ってほしいと思い、ここで販売することにしました。
吉岡さんは、今も制作を続けていますが、ここで販売する作品は今の作品とは作風が異なりヴィンテージならではの魅力があります。
「monokosu」という名前は、”いいモノを残す”という私の思いを込めて名付けました。
須磨張り子とは
須磨張り子とは、神戸市須磨区在住の吉岡武徳さんが制作してきた張り子を指します。ちなみに張り子は、粘土などの型に和紙を貼り重ねて成形する郷土玩具のことです。
▼吉岡さんが須磨張り子を作り始めた経緯
吉岡さんが張り子を制作し始めたきっかけは、民芸品コレクターだった義母へのプレゼントのためだといいます。最初は義母が喜んでくれたのが嬉しくて、教師の仕事と並行して制作活動をしていましたが、義母のコレクションのような素晴らしい作品をいつしか目指すようになり、次第に張り子にのめり込んでいきます。
姫路、大阪、香川(高松)、鳥取(倉吉)、福島など全国の張り子工房訪れ多種多様な作り方を見たうえで、豪快な作風の高松張り子が一番気に入った吉岡さん。高松張り子の職人・宮内フサさんと娘マサエさんの工房に何度か通い、見よう見まねで独自にやり方を模索していった結果、今の作風に至りました。
40歳過ぎから作り始め、40年以上須磨張り子の制作を続けています。
▼神戸の張り子の歴史
元々神戸には伝統的な張り子があったわけではなく、明治から大正にかけて、一人の高松張り子職人が新開地の港で神戸だるまを作り、外国人向けの土産物として販売しており、その後歴史が途絶えたそうです。
吉岡さんは須磨張り子を作り始めてから神戸だるまの存在を知り、姫路の日本玩具博物館にある数少ない現存品をもとに復元させました。
▼須磨張り子の特徴
須磨張り子は地元神戸の民話や六甲山の動物など、ローカルな題材が多く神戸ならではのストーリー性があります。そのほか、「神戸だるま」や「いらっしゃい(両手をあげた招き猫)」など、須磨張り子独自のデザインもあります。
私が思う須磨張り子の魅力は、なんといっても吉岡さんの自由な発想による、面白くてゆるいイラスト・形。綺麗にまとまりすぎていないのが良くて、見ていると思わずふふっと笑顔になれます。
吉岡さんに須磨張り子の特徴を尋ねたら、「手にした人がほっこりする。作るときもほっこりした気持ちでやるようにしている。」とのこと。あ〜だから須磨張り子たちはこんなにやわらかしい表情をしているのか、と納得の答えでした。
神戸須磨張り子公式HP:https://www.eonet.ne.jp/~sumahariko/
monokosuとは
「monokosu」は、いいモノを残すという私の思いを込めて名付けました。
大学・大学院時代まちづくりの研究をしていた私は、北陸の伝統工芸品や山口県の萩焼など、日本各地のモノづくりの現場に触れる機会があり、その美しさに感動するとともに、存続の危機に面している現状を知りました。こんなに可愛くて素晴らしいモノが知られていないままなくなってしまうのは勿体無い、その地に根ざしたいいモノを広めたいという思いが芽生えました。
このmonokosu須磨張り子が、日本中・世界中の可愛いモノたちを広め、残すための活動の第一歩になればいいなと思っています。また、手仕事のモノを家に置いて日々愛でる楽しさを含め伝えていきたいと思います。